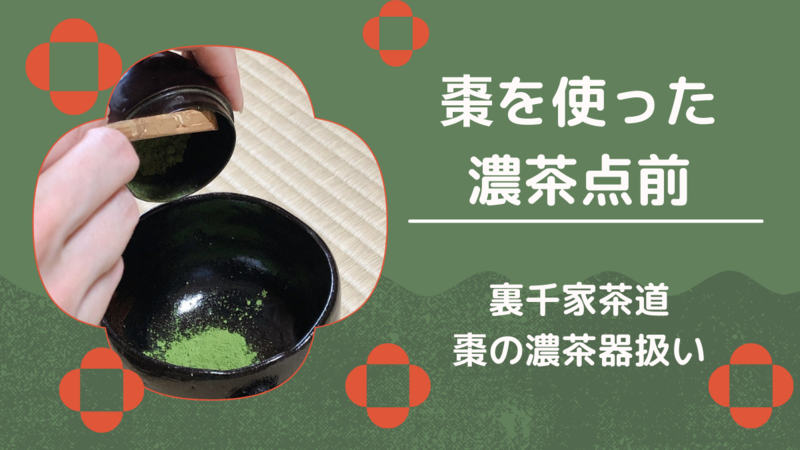


棗はそのままでは薄茶器ですが、大津袋や包み帛紗など、服を着せると濃茶器として濃茶点前で使うことができると前回お伝えしました。
今回は、濃茶点前で棗を使う時の3つのポイントをご紹介していきますね。
棗を濃茶器として使う場合の帛紗のさばき方
濃茶点前で棗を使う場合、帛紗は草に捌くのではなく四方捌きをします。

『四方捌き』より
棗の清め方は基本通り行いましょう。

『棗の清め方』より

棗を使った濃茶点前のお茶の出し方
棗を使った濃茶点前の場合、茶入れのように回し出しはしません。
↓これをしない

『濃茶の運び点前(炉)』より
3杓すくった後、茶杓を棗の内側に当て、そのまま棗を傾けて全部お茶を出し、親指でのみ(下半分のみ)清めます。


棗を使った濃茶点前の拝見の清め方
棗を使った濃茶点前では棗を濃茶器として扱います。
最も大切なポイントは、拝見に出す時の清め方です。
薄茶点前で棗を使うときは、拝見に出す前、帛紗を握りこんで蓋を取りますが、大津袋のお点前の場合は、茶入れと同じように、いったん帛紗を膝前に置いてから蓋を取りましょう。


蓋を「こ」の字に拭き、甲拭きをしたら、一度帛紗を膝正面に置き、蓋を取ります。

帛紗を取り、棗の口を「こ」の字に拭き、再び帛紗を膝前に置いて、蓋を閉めます。


棗を使った濃茶点前のまとめ
- 四方捌きで清める
- 棗なので上から持つ
- お茶を入れるときは回さない
- 下半分だけ拭く
- 清め方は茶入れのようにする
棗なので、持ち方は変わらず上から。
清めるときやお茶を入れるときに少し違ってきますが、していることは今までお稽古してきたことと同じです。
1つ1つの所作をきちんとしていれば大丈夫。慌てずに行いましょう。


\着物でお稽古/
皆さまの応援が励みになっております。
お役に立ちましたら、ポチっと応援よろしくお願いいたします。
↓